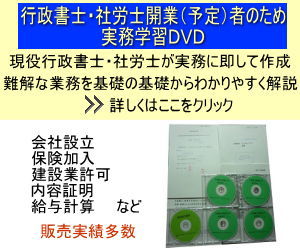巨艦メーカーの猛攻 アイホンが生き残る道は
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コメント
ただいまコメントを受けつけておりません。
巨艦メーカーの猛攻 アイホンが生き残る道は
■【荒木式】がん対策プログラム~元ハーバード大学准教授が考案した画期的な食事法~
「ピンポンは、アイホン」というキャッチコピーを聞いたことはないだろうか。一般的な知名度は低いかもしれないが、アイホンという会社は業界トップシェアを争うインターホン一筋の専門メーカーだ。
【アイホンの売り上げ、営業利益の推移】
愛知県名古屋市に本社を置き、創業約70年。皆さんが普段、何気なく玄関の呼び鈴に使っているインターホンの多くはアイホン製のはずだ。約900億円といわれる国内インターホン市場の大半をアイホンとパナソニックが分け合う。ちなみに、冒頭のキャッチコピーはラジオのオリジナルCMソングの最後に流れている。
同社のビジネスの特徴は、インターホンという特定の商品カテゴリーに集中していることと、自社製品とそのブランドへのこだわりの強さにある。それは同社の歴史と、商標を巡るあのグローバル企業との攻防に表出している。
●Appleとも争ったブランドへのこだわり
アイホンは1948年、先代社長の市川利夫氏が名古屋に東海音響電気研究所を創業したところから始まる。当初はラジオや拡声器の組み立て、修理を行っていた。その後、下請けから脱却し、最終製品メーカーとして生き残る道を模索した。しかし、自社でラジオ製造の準備をスタートした直後に、三洋電機からプラスチックラジオ1号機が発売され、その完成度の高さにアイホンはラジオの製造を断念した。
「大手が手を出さない商品は何か」――。考え抜いた結果が、当時国内メーカーが未参入だったインターホンだったという。1951年にインターホンの生産開始。1952年には愛興高声電話機合資会社に社名変更した(高声電話機とはインターホンのことである)。好景気の波に乗り、旅館や病院などでの引き合いが急増して、飛躍的に業績が拡大していく。1954年、製品名を「アイホン」(社名の一文字“愛”とインターホンのホンを組み合わせた)と改称し、同時に「アイホン」を商標登録している。1956年にナースコールインターホンを納入、1959年には社名もアイホンとした。
既に世に知られている、商標にかかわるエピソードがある。2008年3月、アイホンから「商標に関するお知らせ」というニュースリリースが出た。
「アイホン株式会社は、Apple Inc. と同社の携帯電話「iPhone」(アイフォーン)の商標に関し、弊社が保有する国内および海外の商標権について交渉を行ってきました。このたび、両社は、日本国内においては弊社がApple 社に使用許諾を、日本以外の地域においては両社の商標が共存することで友好的な合意に至りました」
あのAppleのスマートフォン「iPhone」がカタカナ表記で「アイフォーン」になっている所以である。
Appleが米国で初代iPhoneを報道発表したのが2007年1月、発売が2007年6月、日本市場には2008年7月に「iPhone 3G」で参入した。2006年9月には日本で「iPhone」の商標登録を申請したが、既にあったアイホンの登録商標に類似しているとの理由で特許庁が取り下げた。そのためAppleは自社による商標登録をあきらめ、アイホンから独占的使用権を得るために交渉したと推測される。前出のリリースにあるように、AppleのiPhoneのカタカナ表記を「アイフォーン」とすることと、アイホンが「iPhone」の商標をAppleにライセンスすることに合意する。
以来、アイホンはAppleからロイヤリティ収入を得ているようだ。実際、AppleのリリースやiPhoneの外箱の裏には、「商標『iPhone』は、アイホン株式会社の許諾を得て使用しています」と明記されている。
アイホンは海外での事業展開にも積極的で、早くも1970年には米国でAIPHONE U.S.A.、INC.を設立。海外では「AIPHONE」の商標権を得て(日本国内では1966年に英文商標「AIPHONE」登録済)、現在70カ国で製品を販売している。米国においては「ピンポン」というアイホンの呼出音を「音」の商標として登録した。日本でも2014年の商標法改正で、「音商標」が2015年4月から登録できるようになり、「ピンポンはアイホン」の音商標が出願され、現在審査中である。
アイホンは、一貫して大手との差別化を図り、「アイホン」ブランドによってインターホンを一般家庭に普及させた。トップメーカーとして約70年かけて市場を作り上げてきたと言える。しかし、数年前から大手メーカーが本格参入し、その地位が揺らいでいる。
●生き残り戦略
先述したように、国内のインターホンの市場規模は約900億円で、用途別には、住宅向けが89%、そのうちテレビ付インターホンが79%、一般用ドアホンが10%、病院・施設等の業務用が11%となっている(下図)。
2016年度上期は新設住宅着工件数が増加して、主力であるテレビ付インターホン市場は2015年に引き続き増加傾向で推移している。当面は首都圏を中心に大都市圏における集合住宅の増加と、防犯意識の高まりによって、緩やかな市場成長が期待できそうだ。
競合は、総合エレクトロニクスメーカーのパナソニックだ。アイホンと2社で9割以上のシェアを持つと推定される。アイホンの2016年3月期の売り上げは427億円(下図)だが、ここ1~2年で両社の競争が激化、特に戸建新築市場ではパナソニックが優位に立っている。
アイホンの2015年度の売り上げ構成は国内が74%で、そのうち戸建住宅市場が12%、集合住宅市場が40%(図表3)。戸建住宅では同期間に販売台数は増加したものの、価格競争により売上高は対前年96%と苦戦している。一方、集合住宅市場では103%増とし、住宅市場全体では101.4%と、何とか増収を果たした。
国内集合住宅について、新築では大手ハウスメーカーへの密着営業により、小規模マンションやアパート向けシステム販売が好調。リニューアルでは、既設配線が利用でき、かつ施工性を高めた新しい集合住宅システムの販売が増加。ハウスメーカーや設計事務所、工務店の現場ニーズをくみ取ったシステム型の商品と提案営業による成果と言える。
かたや、同社の戸建市場での苦戦は、「価格.com」サイトを見ると、その一端を垣間見ることができる。ライバルのパナソニックの圧倒的な品揃えと価格帯の広さ、加えて低価格化である。そこではアイホンの存在感は小さい。住宅のニーズが新築からリニューアルにシフトし、個人主導でインターホンが設置されるようになると、アイホンの強みだったハウスメーカーや設計事務所向けの営業は生きず、消費者対応が求められる。家電流通における消耗戦を少しでも回避するには、ネット対応と最終消費者向けのブランド再構築が必要だろう。
そのほか、成長市場として期待されるケア市場(病院、高齢者施設や高齢者住宅)でも、着工件数の減少、高齢者施設での競争の激化により売り上げは減少している。成長をけん引しているのは、海外市場、特に北米での伸長である。1970年の米国進出を皮切りに、現在は約70か国以上で販売され、海外比率が約3割までに拡大している。中でも北米市場は115%と2桁成長である。
●国内市場でビジネスを再構築
今後の方針として、2016年度スタートの中期経営計画でも示されているように、北米市場中心に海外拠点の拡大に積極的に取り組んでいくのは当然と言える。一方で、売り上げの7割を超える日本市場で再度強みを再構築することが最大の課題である。
重点とすべきは、アイホンの強みを生かす集合住宅でのシステム型商品によるハウスメーカーとの取り組み、セキュリティ関連サービスとしてのプラットフォームビジネスへ挑戦することだ。
「アイホン」ブランドはアイホンのコアとなっている。しかし、そのブランド認知はまだまだ業界関係者と名古屋都市圏居住者に止まっている。今後、国内市場においてアイホンが生き残るためには、なおのこと消費者にとって商品サービスを選ぶ際の「選択の手掛かり」となるブランドとして、あらゆる接点を通じて、新しいメッセージを届けることが求められているのだ。
(大場美子)
コメント
ただいまコメントを受けつけておりません。