できたて提供 ローソン「まちかど厨房」開発に込めた思い
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コメント
ただいまコメントを受けつけておりません。
できたて提供 ローソン「まちかど厨房」開発に込めた思い
■【荒木式】がん対策プログラム~元ハーバード大学准教授が考案した画期的な食事法~
ローソンは、店内で調理した弁当やサンドイッチなどを販売する「まちかど厨房」を全国約3500店舗に展開している。厚さ2センチのとんかつを挟んだ「厚切りロースかつサンド」などが人気の商品だ。店内厨房の開発や全国展開を進めてきた、まちかど厨房担当部長の鷲頭裕子(わしず・ひろこ)さんが大切にしているのは「現場感」。店舗経営にメリットのある仕組みを模索し続けながら、実施店舗を広げてきた。
【店内厨房の様子】
●おにぎりから挑戦
まちかど厨房の展開は2011年に始まったが、実はそれ以前にも弁当を店内で調理する取り組みがあった。最初は04年に始めた「できたて弁当」。中堅コンビニで店内調理の弁当やパンを販売する店舗はあったが、大手では珍しかった。「競合店がやらないことをやる」ことを目的に開発した。その後も店内厨房の事業モデルの開発と失敗を繰り返した。カウンター内に本格的なライブキッチンを構え、来店客の見えるところでフライパンを振るパフォーマンスを取り入れたことも。飲食店の協力でレシピや食材をそろえた。しかし、実施店舗は全国で50店舗以下と、広がらなかった。十分な広さと人員が必要だったため、コンビニの店舗形態で導入するのは難しかったのだ。
鷲頭さんは、九州や四国などで実務経験を積み、09年に東北商品部に赴任。東北エリアの厨房事業を担当することになった。東北では、競合に対抗する施策だけでなく、過疎化に対応する取り組みも求められていた。スーパーが減ってしまった地域では、コンビニがその代わりにならなければならない。そのための取り組みとして、地域モデルの店内厨房開発に挑戦することにした。
全国的に広がらなかった店内厨房モデルには、厨房スペースを確保するための店舗規模と調理を担う人材が必要だった。鷲頭さんらは、その負担をできるだけ減らした簡易モデルの開発を目指した。まず、うどんとそばを調理する厨房の開発を試みたが、採算が合わずに頓挫。厨房設備などをさらに簡易にしたおにぎりから取り組むことにした。
おにぎりを作るだけなら、厨房に必要な設備は炊飯器などに限られる。投資金額は、既存モデルの3分の1に抑えられた。多くの店舗で展開しやすい厨房にするため、商品を絞り込んだ。
また、「おにぎりができれば、弁当やパンにステップアップしやすい」と鷲頭さんは考えていた。その理由は、おにぎりが簡単だからではない。逆に、手作りのおにぎりは他の商品より難しいからだ。ご飯を炊いて手で握るという、家庭の作り方と近いおにぎりを提供するのは、手間がかかる。そのおにぎりを効率的に、おいしく作るモデルを確立できれば、他の商品にも手を広げられる。実際に、おにぎりから調理パン、弁当へと段階的にメニューを広げることができた。
簡易モデルの店内厨房は3年で広まり、東北地方の店舗の半分程度が設置するまでになった。厨房事業の経験を積んだ鷲頭さんは、12年に本社に異動。本社で取り組んでいた事業モデルと、地方で生まれた簡易モデルを組み合わせた「まちかど厨房」の事業に携わることになった。
●加盟店の武器に
新たな事業モデルとなる、まちかど厨房の開発の目的は、「店内厨房の実施店舗を広げること」。根強く残る「大変」というイメージを変え、「加盟店の“武器”になるもの」にすることが必要だった。設備や商品などに工夫を加えることで、パッケージ化できる仕組みの構築を目指した。
例えば、メニューごとにバラバラだった弁当の容器を統一したり、汎用性のある包装フィルムを採用したりと、細かい作業の煩雑さを減らすことに取り組んだ。また、メニューも簡単にした。店内厨房で揚げるとんかつを複数の商品に使用するようにしたほか、飲食店と共同開発したカレーなどをラインアップに加えた。おいしさを維持しながらも、パッケージ化して商品の幅を広げた。
しかし、システムが変わっても「大変」「手間」というイメージは根強く残っていた。弁当の店内調理が少数店舗の取り組みだったころ、本社と店舗の間で情報共有が十分にできておらず、その状態が続いていたからだ。本社には「現場感がなかった」という。
そこで、鷲頭さんの経験が生きた。地方勤務で学んだ、現場で発生する細かい問題やそれを解決する知恵などを、各店舗を回るスーパーバイザーに教え、加盟店に伝える情報として活用してもらった。また、新しい店内厨房がどんなものであるのか、伝えるための研修なども実施し、イメージを変えることを目指した。
●困りごと解消も
現場からの声も重視した。少数意見だとしても、「反応してくれる人に対して、しっかりと対応する」ことを心掛け、困りごとの解消に努めた。その一環として、固定費を削減するため、複数設置されていたラベルシール発行の機器を集約。余計なランニングコストがかかる設備を減らした。
細かいことに目を配る行動の背景には、東北時代の失敗がある。他のエリアの店舗に店内厨房の簡易モデルを教える機会があったが、うまく伝わらなかった。店舗の状況や運営する環境が東北と異なり、同じノウハウを共有することが難しかったのだ。細部にわたって環境を整えることの大切さを学んだ。
今では、できるだけ「細部にわたって伝える」ようにしている。厨房機器の配置や実際の作業を具体的にイメージできるような情報に加え、店舗への負担などのマイナス情報も明確に伝えるようにしている。「耳障りのいいことばかり言っていてはだめ。プラスマイナスをセットにして判断してもらう」という。
店舗の利益に大きく貢献する事業に育てるための課題はまだ多い。しかし、「(店内厨房が)簡単になった」と喜んでもらえることも増えた。今では、まちかど厨房の商品が、1店舗当たり1日平均1万5000円の売り上げとなっている。
●地域のインフラにも
今後も「(加盟店に)もうかってもらうためのネタを提供し続けたい」と語る鷲頭さん。厨房設備やメニューなど、同じものを使って販売しても、店によって売り上げに差がある。「この店ではなぜ売れるのか」「どういったオペレーションをすれば利益を出せるのか」といった理由を十分に伝えることができていないと感じている。効率化の方法や生産性を向上させる仕組み、売れる時間帯など、「もっと分析していかないと」と意気込む。商品の作り方を改善するヒントを集めるため、毎月店舗を回っている。
「環境の変化は激しく、5年後どうなるか分からない。良くなってもそれに満足せず、商品やオペレーションに関する仮説を立てて、早めに実験して、適切なタイミングで提案していきたい」と先を見据える。
鷲頭さんは店内調理の事業に必要性を見いだしている。その背景には、東北在任中の11年に経験した東日本大震災がある。ローソンの店内厨房にコメも水もあったため、いち早くご飯を炊いて、温かい食べ物を提供できた。「人は温かいものを食べると、幸せを感じる。店内厨房は有事の際に強みになると確信した。やめないで続けていくべき事業だ」。災害時に野菜の仕入れができない状況に備え、キャベツを入れないカツサンドの商品ラベルも常に用意しているという。
インフラとしての機能を備え、店舗経営にとってもメリットのある仕組みを構築できれば、地域社会に必要とされる事業として継続していけるだろう。鷲頭さんは、まちかど厨房をさらに大きく育てるため、加盟店にも地域の人々にも喜ばれる仕組みを追求し続けていく。
引用:できたて提供 ローソン「まちかど厨房」開発に込めた思い
PR___________________________________
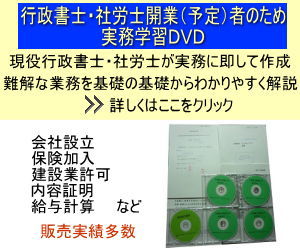 ________________________________________
________________________________________
コメント
ただいまコメントを受けつけておりません。
