「QRコード」の新たな活用方法 翻訳アプリやふるさと納税、認知症対策など
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コメント
ただいまコメントを受けつけておりません。
「QRコード」の新たな活用方法 翻訳アプリやふるさと納税、認知症対策など
■【荒木式】がん対策プログラム~元ハーバード大学准教授が考案した画期的な食事法~
スマートフォンの読み取りアプリなどをかざせば、瞬時に情報が入手できる便利な「QRコード」。誕生は1994年の日本、生みの親はデンソーの開発部門(現デンソーウェーブ/本社:愛知県知多郡)。とかくガラパゴスと揶揄されがちの日本発の技術にあって、こちらはいまや世界標準となったマトリックス型二次元コードだ。そして世に送り出されて20年以上が経過した今、日本ではさまざまな場面でQRコードが使われている。
翻訳された飲食店メニュー(韓国語) QRコードを使って「翻訳」をサポートする。訪日観光客は増えているが、問題はコミュニケーション。そこでQRコードを活用したのが、一般社団法人タグフィット(福岡県福岡市)の提供する「コトつなカメラ」。こちらはスマートフォン向け無料翻訳アプリだ。使い方は簡単で、もし飲食店がメニュー表に日本語以外の表記も加えたいと思えば、アプリを起動し現状のメニュー表を撮影して送信する。これだけで外国語への翻訳が行われ、QRコードが発行される。このQRコードをお店の必要な場所に設置しておけば、それぞれの言語で内容を確認できるようになる。店舗のインバウンド対策に、今後ますます需要が高まりそうだ。
地方の元気をサポートするきっかけにも活用されている。このところ人気の「ふるさと納税」だが、利用者の大半はインターネットを頻繁に活用する層だという。そこで、もっと幅広く多くの人が気軽にと現れたのが「ふるさと納税自動販売機」。販売商品は水などご当地の1本で、商品容器には飲料の産地のふるさと納税を紹介するウェブサイトにつながるQRコードが付いている。2016年春の深谷市(埼玉県)を皮切りに、美濃加茂市(岐阜県)、東京都と全国に広がっており、地方の“懐事情”の渇きを癒すことになりそうだ。旗ふり役はふるさと納税情報ウェブサイト「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンク(本社:東京都渋谷区)。
増える認知症高齢者の徘徊によって起きる不測の事態に、急がれる対策の整備。ここでも熱い視線が注がれているのがQRコードだ。オレンジリンクス(本社:埼玉県入間市)が開発した「爪Qシール」は、人の手や足の爪に貼る身元確認用のQRコードで、通常の生活ではまずはがれない。同QRコードから読み取れる情報は、居住する自治体名と連絡電話番号、そして身元確認番号。自宅の電話番号といった個人情報は、第三者の悪用を避けるために盛り込まれていない。昨年末からは、同社のある入間市で、全国初「徘徊SOS支援事業(身元確認支援サービス)の一環として採用された。
QRコードの新たな活用方法の提案は、今後もまだまだ続きそうだ。
引用:「QRコード」の新たな活用方法 翻訳アプリやふるさと納税、認知症対策など
PR___________________________________
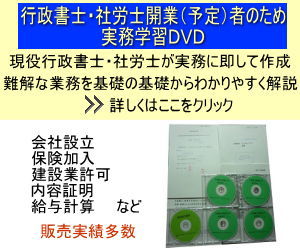 ________________________________________
________________________________________
コメント
ただいまコメントを受けつけておりません。
